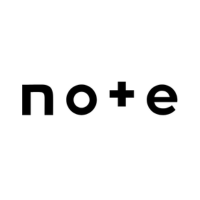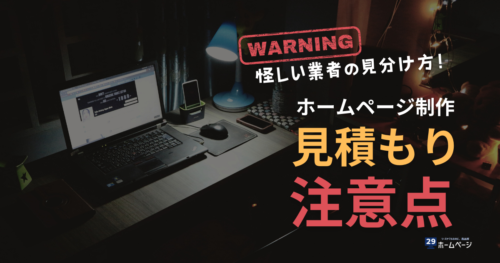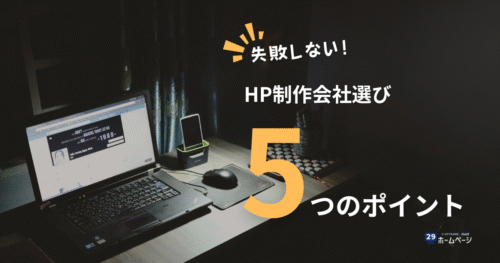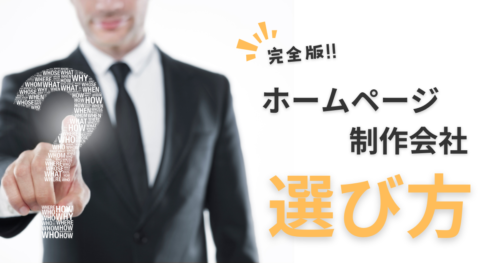ホームページ制作見積もりの注意点|制作会社選びに失敗しない全知識
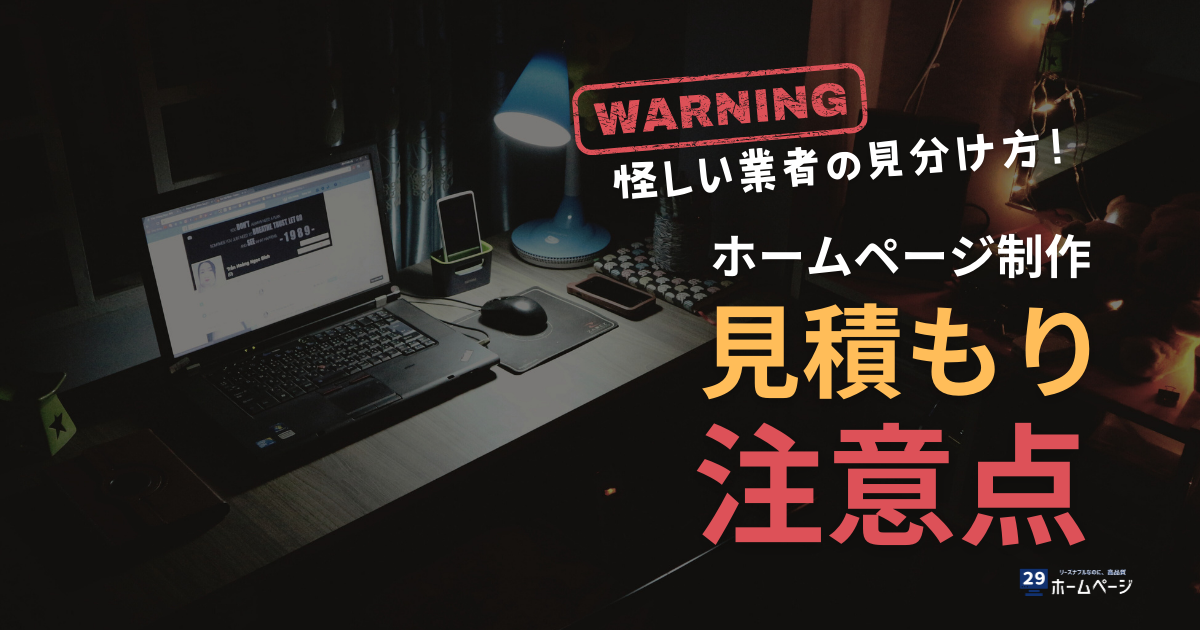
ホームページ制作の見積もりを検討しているけど

後から高額な追加費用を請求されたらどうしよう…
と、不安な方もいるかもしれませんね。
でも、大丈夫ですよ!実は、注意すべきポイントは意外とシンプルなのです。
大切なのは「作業範囲」「追加費用」「相見積もり」、この3つをしっかり確認すること。
このポイントさえ押さえれば、後で「こんなはずじゃなかった…」と後悔するリスクをぐっと減らせますよ!
- 見積もり前に失敗を防ぐ準備の進め方
- 見積書の項目別チェックポイントと注意点
- 怪しい業者や危険な見積もりを見抜く方法
ホームページ制作の見積もりは、ポイントさえ知っておけば決して怖いものではありません!
ぜひこの記事を参考にして、安心して理想のホームページ作りを進めてくださいね!
ホームページ制作の見積もり、不安ですよね?
ホームページ制作の見積もり、専門用語が多くて戸惑いますよね。



僕もフリーランスとしてホームページ制作を始める前は、正直チンプンカンプンでした…。
金額も決して安くないですし、「これで本当に大丈夫なのかな?」「後から高額な請求が来たらどうしよう…」と不安になる気持ち、すごくよく分かります!
でも、安心してくださいね。
いくつかの大切なポイントを押さえておけば、見積もりに対する不安はずいぶん軽くなりますよ。
この章では、まず「なぜホームページ制作の見積もりは分かりにくいのか?」、そして「見積もりで失敗しないための重要ポイント」について、僕の経験も踏まえながらお伝えしていきますね!
なぜホームページ制作の見積もりは分かりにくい?
ホームページ制作の「見積もりが分かりにくい」と感じるのには、いくつか理由があるんです。
- ホームページ制作は、専門性が高いため
- 価格設定の基準が、業者によってまちまちなため
- お客様側に、専門知識があまりないことが多いため
ホームページ制作って、実はデザインを作るだけじゃなくて、
- 設計(ディレクション)
- 見た目を作る(デザイン)
- 動きを作る(コーディング)
- 記事などを更新する仕組み(CMS構築)
上記のように、色々な工程があるんですね。
それぞれの工程に専門的な技術や知識が必要で、その費用が積み重なって見積もり金額になります。
でも、



ディレクション費って具体的に何をしてくれるの?
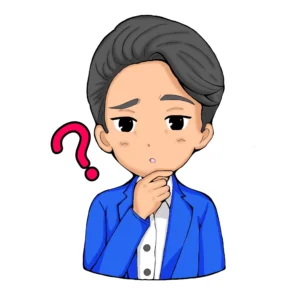
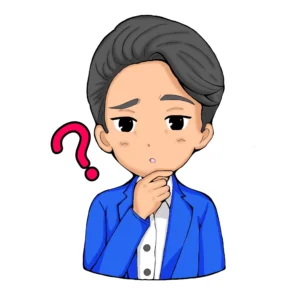
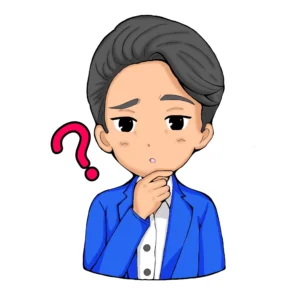
このCMS構築費って妥当な金額なの?
というように、項目名だけ見ても内容や相場が分かりにくいことが多いですよね…。
さらに、業者さんによって得意なことや価格の付け方が違うので、



A社とB社で見積もり内容が全然違う…!
なんてこともよくあります。
どこまでの作業が含まれていて、何が含まれていないのか、その線引きが曖昧な見積書も残念ながら存在するのが実情かもしれません。
だから、分かりにくいと感じるのは、決してあなただけではありません。
失敗談から学ぶ、見積もりのリスク
見積もりの内容をよく確認せずに進めてしまうと、後で



こんなはずじゃなかった・・・
というトラブルに見舞われる可能性があります。
これは本当に避けたいですよね…。
僕が見聞きした範囲や、よくある失敗例としては、次のようなケースが挙げられます。
- 想定外の追加費用
契約時には想定していなかった作業が発生し、後から高額な追加費用を請求される。「ちょっとした修正」のつもりが、大きな金額になってしまった…。 - 完成イメージとの乖離
完成したホームページが、思っていたデザインや機能と全然違う。特に、作業範囲の確認が甘いと起こりがちです。 - 納期の遅延
約束の納期を過ぎてもホームページが完成しない。オープン予定が狂ってしまったり、ビジネスチャンスを逃したりすることも…。 - 連絡がつかなくなる
制作途中で担当者と連絡が取れなくなったり、質問への返信が極端に遅くなったりする。 - 契約内容での不利
更新や修正に高額な費用がかかる契約になっていたりする。後から気づいても変更が難しい場合も。
これらのリスクは、見積もり段階でのちょっとした確認不足から生じることが多いんです。
しっかり対策していきましょう!
ホームページの見積もり、3つの重要ポイント
ここまで読んで、



やっぱりホームページ制作って怖い…
と、感じてしまったかもしれません。
でも、大丈夫です!
見積もりで失敗しないために、絶対に押さえておくべき超重要なポイントが3つあります。
- 作業範囲の明確さ
どこまでやってくれるのか?何が含まれているのか、いないのか? - 追加費用の条件
どんな場合に、いくら追加費用がかかるのか? - 契約内容
権利関係(著作権など)、納期、支払い条件、検収方法、公開後の保守はどうなるのか?
なぜこの3つが重要かというと、先ほど挙げた失敗談のほとんどが、この3点の確認不足から起こっているからです。
作業範囲が曖昧だと、「言った」「言わない」の認識のズレが生まれやすいですし、追加費用の条件が不明確だと、予期せぬ出費に繋がります。
契約内容をしっかり確認しておかないと、後々不利な条件に縛られてしまう可能性だってあるんですね。
逆に言えば、この3つのポイントさえしっかり確認しておけば、



見積もりに関するトラブルの大部分は防げる
と、僕は考えています。
これから先の章で、これらのポイントを具体的にどうチェックしていけば良いのか、詳しく解説していきますね!
まずは、この3つが「見積もり確認のキモ」だと覚えておいてください。
見積もり依頼で失敗しない!最初にやるべき準備【超重要】



さあ、いよいよホームページ制作に向けて動き出すぞ!
と、意気込んでいるあなた。
その前に、ちょっと待ってくださいね。
実は、制作会社に見積もりを依頼する「前」の準備が、後々の成功を大きく左右するんです!



僕もフリーランスとして活動していて痛感しますが、ホームページ制作の依頼前の準備をしっかりやっておくと、お互いの認識のズレが少なくなり、ホームページ制作がスムーズに進みやすいんですよ。
逆に、準備不足のまま依頼してしまうと、



思っていたのと違う…



もっとこうしてほしかったのに…
なんてことになりかねません…。
特に初めてホームページを作る方や、以前に苦い経験がある方は、不安が大きいかもしれませんね。
でも、大丈夫。
この章でお伝えする3つの準備をしっかり行えば、自信を持って見積もり依頼に進めますよ!
まずは目的を整理しよう「どんなホームページにしたい?」
何よりもまず最初にやるべきこと、それは「何のためにホームページを作るのか?」という目的を明確にすることです。
これが全ての土台になります。
なぜなら、目的が曖昧なままでは、どんなデザインが良いのか、どんな機能が必要なのか、制作会社も判断できないからです。
結果として、出来上がったホームページが「ただ作っただけ」のものになってしまい、期待した効果(例えば集客や売上アップ)に繋がらない…なんてことにもなりかねません。
例えば、あなたがレストランのオーナーさんなら、



新規のお客さんに来てもらいたい



電話だけでなくネット予約も受けつけたい
といった目的があるかもしれませんね。
フリーランスのデザイナーさんであれば、



クライアントに自分の作品を見てもらって、仕事の依頼を受けたい
という目的かもしれません。
このように、「誰に、何を伝えて、どうなってほしいのか」を具体的に考えてみましょう。
難しく考えなくて大丈夫ですよ。
箇条書きでメモするだけでも全然違います。
目的がはっきりしていると、制作会社にも的確な要望を伝えられますし、見積もりの内容もより具体的になります。



僕自身の経験からも、目的が明確だとホームページ制作の途中でブレにくくなるので、ここは時間をかけて考えてみることをおすすめします!
制作会社への要望リスト作成のコツ
ホームページを作る目的がはっきりしたら、次はそれを具体的な「要望リスト」に落とし込んでいきましょう。
これも、制作会社との認識のズレを防ぐために、とても重要な作業になります。
口頭で伝えるだけだと、どうしても伝え漏れがあったり、「言った」「言ってない」といった食い違いが起こりやすかったりするんですね…。
では、どんなことをリストにまとめれば良いのでしょうか?
これも完璧を目指す必要はありません。
思いつく範囲で、以下のような項目を書き出してみると良いでしょう。
- 必須だと思う機能
例)お問い合わせフォーム、ブログ機能、予約システム、オンライン決済、会員登録機能など。店舗経営者なら「予約システム」、デザイナーなら「ポートフォリオを見せる機能」「ブログ」などが考えられますね。 - 参考になるサイト
「こんな雰囲気のサイトがいいな」「このサイトのこの部分が好き」というような、イメージに近いホームページがあれば、いくつかURLをリストアップしておきましょう。 - デザインのイメージ
希望する色合い(例:暖色系、青を基調に)、雰囲気(例:シンプル、高級感、親しみやすい、スタイリッシュ)、ターゲット層(例:30代女性、中小企業経営者)などを伝えられると、よりイメージが共有しやすくなります。 - ページ構成(サイトマップ)
どんなページが必要か、ざっくりとで良いので書き出してみましょう。(例:トップページ、サービス紹介、料金、実績紹介、会社概要、お問い合わせ、ブログ) - CMS(コンテンツ管理システム)の希望
自分でブログやお知らせを更新したい場合は、「WordPressを使いたい」など希望を伝えておくと良いでしょう。特にデザイナーやコンサルタントの方は、更新性を重視するかもしれませんね。 - 素材(写真・文章)
ホームページに載せる写真や文章を自分で用意するのか、制作会社に依頼したいのかも伝えておくとスムーズです。
「こんなこと書いてもいいのかな?」と思うような希望でも、とりあえず書いてみてください。
それが制作会社にとって、良い提案のヒントになることもありますよ。
本格的なRFP(提案依頼書)を作るのは大変ですが、まずは簡単なメモから始めてみましょう!
予算はどう決める?制作会社への正直な伝え方と注意点
さて、目的と要望がある程度まとまったら、次はいよいよ「予算」についてです。
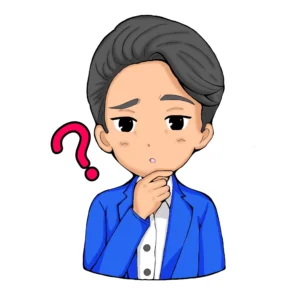
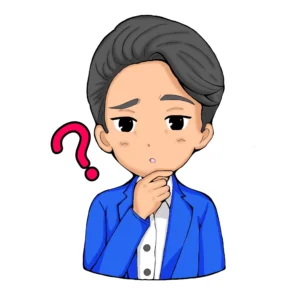
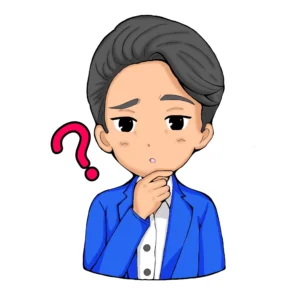
予算を正直に言うと、足元を見られるんじゃないか…



安く言って、後で交渉しようかな…
なんて考えてしまう気持ち、少し分かります。
でも、僕の経験上、予算はできるだけ正直に伝えた方が、結果的に良い関係を築けて、満足のいくホームページができる可能性が高いんです。
なぜかというと、制作会社は予算が分かれば、その範囲内で実現可能な最大限の提案を考えやすくなるからです。
例えば、予算50万円と100万円では、提案できるデザインの自由度や機能、かけられる工数が変わってきます。
予算を伝えないと、制作会社は手探りで提案することになり、結果的に予算オーバーの提案になったり、逆に物足りない提案になってしまう可能性もあります。



予算を正直に伝えることで、お互いに現実的な話を進めることができるんですね。
予算の決め方ですが、まずは作りたいホームページの種類(コーポレートサイト、お店のサイト、ポートフォリオサイトなど)の一般的な相場を調べてみましょう。
その上で、「いくらまでなら出せるか」という上限を決めるのが良いと思います。
関連記事
≫ ホームページ制作費用を抑えたい個人事業主へ。相場と格安術を公開
伝える際は、



今回のホームページ制作の予算は、〇〇円程度で考えています。この予算内で、私たちの要望を最大限叶えるには、どのようなご提案が可能でしょうか?
といった聞き方をすると、建設的な話し合いに繋がりやすいですよ。
あまりにも相場とかけ離れた低い予算を提示するのは、質の低い提案しか受けられなかったり、そもそも相手にされなかったりする可能性があるので避けましょう。
また、1社だけでなく、複数の会社から見積もりを取る「相見積もり」も有効です。
相見積もりによって、適正な価格感や、各社の提案内容、担当者との相性などを比較検討できますからね。
予算が限られている場合は、



予算は〇〇円と限られているのですが、どうしても〇〇(目的)を実現したいです。何か工夫できる点はありませんか?
このように、正直に相談してみるのが良いと思います。
僕自身も格安でホームページ制作を提供していますが、予算が厳しい中でも工夫次第で良いものを作ることは可能だと考えています。
ただし、できることには限界もあるので、正直なコミュニケーションが何より大切ですね。
見積書が届いたらココをチェック!項目別の注意点【実践編】



制作会社さんから見積書が届きました!
さあ、いよいよここからが本番!しっかり内容をチェックしていきましょう。
専門用語が並んでいて、ちょっと圧倒されてしまうかもしれませんが、大丈夫です。
この章では、見積書を受け取った後に具体的にどこをどう見れば良いのか、項目別に注意点を解説していきますね。
見積書をしっかり確認するかどうかで、後々の満足度が大きく変わってきます。



一緒に一つずつ見ていきましょう!
「一式」は危険信号?作業範囲と内訳を必ず確認しよう
見積書を見て、まず最初に注意してほしいのが「一式」という表記です。
もし、「ホームページ制作費 一式 〇〇円」のように、ざっくりとした項目しかない場合は、ちょっと注意が必要かもしれません。
なぜなら、この「一式」の中に具体的にどんな作業が含まれていて、何が含まれていないのかが全く分からないからです。
これだと、後になって



え、この作業は含まれていなかったんですか?



それは別料金になります
こんな風に、言われてしまうリスクが高いんですね…。
ですから、見積書では、できるだけ作業の内訳が細かく記載されているかを確認することが鉄則です!
具体的には、以下のような項目があるか、そしてそれぞれの内容が明確かを見ていきましょう。
- ディレクション費
プロジェクト全体の進行管理や打ち合わせ、企画構成などにかかる費用です。どんな内容の管理をしてくれるのか確認しましょう。 - デザイン費
ホームページ全体のデザイン作成、トップページ、下層ページのデザインなど、どこまでの範囲のデザインが含まれるか確認が必要です。 - コーディング費
デザインを元に、実際にWeb上で表示されるようにプログラムを組む作業の費用です。どのページをコーディングするのか、範囲を確認しましょう。 - CMS構築費
WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)を導入し、自分で更新できるように設定する費用です。どのCMSを使うのか、どんな設定が含まれるのか確認します。 - サーバー・ドメイン関連費
ホームページを公開するためのサーバー契約やドメイン取得の代行費用などです。自分で用意するのか、制作会社が手配してくれるのか確認しましょう。 - 素材費
写真やイラストなどの素材を使用する場合の費用です。有料素材を使うのか、フリー素材なのか、自分で用意する必要があるのかなどを確認します。 - その他
お問い合わせフォーム設置費、基本的なSEO設定費、スマホ対応(レスポンシブ対応)費などが別途記載されている場合もあります。
もし、「一式」表記が多かったり、項目名だけでは内容がよく分からなかったりする場合は、遠慮なく制作会社さんに質問しましょう!



この『デザイン費』には、具体的にどのページの作成が含まれますか?



『CMS構築費』では、どのような機能が使えるようになりますか?
といった具合です。
良い制作会社さんであれば、丁寧に説明してくれるはずですよ。
僕自身が見積もりを作成する際も、できるだけお客様に分かりやすいように、作業内容を具体的に記載することを心がけています。
デザイン修正は何回まで?
特にデザインにこだわりたい方にとっては、非常に重要な確認ポイントです。
見積もりの中に、デザインの修正に対応してくれる回数や範囲が明記されているか、必ずチェックしましょう。
なぜこれが重要かというと、修正に関するルールが曖昧だと、後々トラブルになりやすいからです。
例えば、「納得いくまで修正します!」と言われても、際限なく修正依頼をしてしまってはプロジェクトが進みません。
逆に、「修正は1回までです」と厳しく制限されていると、最終的に満足のいくデザインにならない可能性もあります。
また、「ちょっとした修正」のつもりが、「これは大幅な変更なので追加料金です」と言われてしまうケースも考えられます。



そうならないように、見積もりの段階で、以下のような点を確認しておきましょう!
- 修正可能な回数
トップページのデザイン案は何回まで提案してくれるのか? 各ページのデザイン修正は何回まで可能なのか? - 修正可能な範囲
どの段階での修正が対象なのか?(例:ワイヤーフレーム(骨組み)段階、デザインカンプ(完成イメージ)段階など) テキストの修正や画像の差し替えは回数に含まれるのか? 大幅なレイアウト変更は可能か? - 修正依頼の方法
どのように修正を依頼すれば良いのか?(例:メール、チャットツール、打ち合わせなど)
上記の内容は、「デザイン費」の項目や、契約条件の欄に記載されていることが多いです。
もし明記されていない場合は、



デザインの修正は何回まで可能でしょうか?



どの段階での修正が対象になりますか?
と、質問しましょう。
スマホ対応は?機能は?見積もりに含まれる作業をリストアップ
今の時代、ホームページはパソコンからだけでなく、スマートフォンやタブレットから見られることがほとんどですよね。
ですから、「スマホ対応(レスポンシブデザイン)」が見積もりに含まれているかは、絶対に確認すべき必須項目!
また、あなたのホームページに必要な「機能」がちゃんと含まれているかも、リストアップして確認することが大切です。
これらを確認しないと、



せっかく作ったのにスマホだと見づらい…



欲しかった機能が、追加料金になった…
なんてことになりかねません。
具体的に、以下のような項目が見積もりに含まれているか、チェックリストを作って確認してみましょう。
- レスポンシブデザイン対応
スマートフォン、タブレットなど、異なる画面サイズで最適に表示されるか? - 基本的なSEO設定
タイトルタグやメタディスクリプションの設定など、検索エンジンに見つけてもらいやすくするための基本的な設定は含まれるか? - お問い合わせフォーム
必須機能の一つ。お問い合わせフォームの設置は、見積もりに含まれているか? - ブログやお知らせ更新機能
自分で情報発信したい場合に必要。CMSの導入は、見積もりに含まれているか? - 予約システム
飲食店やサロンなど、予約が必要な業種の場合。外部サービス連携か、オリジナル開発か? - オンライン決済機能
商品販売やサービス利用料の決済が必要な場合。どの決済サービスに対応するか? - その他
地図の埋め込み、SNS連携、アクセス解析ツールの導入など。
これらの項目は、「入っていて当たり前だろう」と思っていても、意外と含まれていなかったり、オプション扱い(別料金)だったりすることがあります。



この見積もりには、レスポンシブ対応は含まれていますか?



お問い合わせフォームの設置もお願いできますか?
このように、一つずつ具体的に確認していくことが、後々の「しまった!」を防ぐ一番の方法ですよ。
要注意!「追加費用」を防ぐための確認ポイント
ホームページ制作を進めていると、「やっぱりここをこうしたい」「この機能も追加したい」といった要望が出てくることは、実はよくあることです。
変更や追加について「どこまでが見積もり範囲内で、どこからが追加費用になるのか」という線引きが曖昧な場合は、問題が起こりやすいので要注意!
予期せぬ追加費用は、予算オーバーに直結しますし、制作会社への不信感にも繋がってしまいますよね…。
これらを防ぐためには、見積もり段階で「どんな場合に」「どのくらいの」追加費用が発生するのか、その条件を明確にしておくことが非常に重要です。



以下の点について、しっかり確認しておきましょう。
- 追加費用が発生する具体的なケース
- 大幅な仕様変更
(例:当初予定になかった機能の追加、デザインコンセプトの根本的な変更) - デザインの大幅な修正
(例:規定回数を超えた修正、決定後のデザイン変更) - 提供する原稿や写真素材の提出遅延
- ページ数や掲載コンテンツ量の大幅な増加
- 契約範囲外の作業依頼
(例:ロゴ制作、写真撮影、文章作成など)
- 大幅な仕様変更
- 追加費用の算出基準
時間単価なのか、作業項目ごとの単価なのか? 事前に見積もりを出してもらえるのか? - 変更・追加依頼の手順
どのように依頼すれば良いのか? 変更内容と費用の承認プロセスはどうなっているのか?
これらの条件は、見積書だけでなく、契約書や利用規約などに記載されている場合もあります。
もし記載が見当たらない、あるいは内容が曖昧だと感じたら、



どのような場合に、どのくらいの追加費用が発生する可能性がありますか?
とストレートに質問してみましょう。
ここを曖昧にしたまま契約してしまうと、後で



こんなはずじゃなかった…!
と、揉める大きな原因になります。
事前にルールを明確にしておくことが、お互い気持ちよくプロジェクトを進めるための鍵ですよ。
サイト公開後の運用も考えよう
ホームページは、作って公開したら終わり、ではありません。
むしろ、公開してからがスタートと言っても過言ではないくらい、その後の運用が大切になってきます。
ホームページ公開後にやるべきことは、例えば次の通り。
- サーバーやドメインの契約更新
- セキュリティ対策、ソフトウェア(CMSやプラグイン)のアップデート
- 定期的なバックアップ
- 新しい情報の発信や内容の更新など
ホームページ公開後にも、意外とやるべきことって多いんです。
ですから、見積もりをチェックする際には、「サイト公開後の保守・運用」について、どこまでサポートしてくれるのか、費用はいくらかかるのかも確認しておくことをおすすめします。
特に、ITにあまり詳しくない方や、本業が忙しくてサイト運用に時間を割けない方にとっては、重要なポイントになりますね。



以下の点について確認してみましょう。
- サーバー・ドメインの管理
サーバー代やドメインの更新費用は見積もりに含まれているか? 更新手続きは誰が行うのか?(自分で管理するのか、制作会社に任せるのか) - CMS・プラグインのアップデート
WordPressなどを使用する場合、本体やプラグインのアップデート作業は対応してくれるのか? 費用は? - セキュリティ対策
不正アクセスや改ざんを防ぐための対策は含まれているか?(例:セキュリティソフト導入、定期的な監視) - バックアップ
定期的にサイトデータのバックアップを取ってくれるか? 復旧作業は可能か? - 更新サポート
簡単なテキスト修正や画像の差し替えなど、どの程度の更新作業を、どのくらいの頻度で、いくらで対応してくれるのか?
保守・運用については、見積もりに含まれず、別途「保守契約」として提案されるケースも多いです。
その場合は、契約内容(サポート範囲、対応時間、費用など)をしっかり確認しましょう。



自分でできることは自分でやりたい



専門的なことはプロにお任せしたい
など、あなたの希望に合わせて、必要なサポート内容と費用を確認しておくことが大切です。
公開後のことまで考えておくことで、安心してホームページを育てていけますよ。
その見積もり、本当に大丈夫?怪しい業者を見抜く方法
見積書の内容を細かくチェックするのも大切ですが、そもそも「その見積もりを出してきた制作会社さん、本当に信頼できるの?」という視点も忘れてはいけません。
せっかくお金と時間をかけるのですから、「騙されたくない」「損をしたくない」と思うのは当然ですよね。
この章では、ちょっと怪しいかもしれない業者の特徴や見抜き方、そして信頼できるパートナーを見つけるためのポイントについて、具体的にお伝えしていきますね!
安すぎ?高すぎ?ホームページ制作費用の相場と価格の裏側
見積もり金額を見たとき、



あれ、思ったより安いな



うわ、結構高いな…
と、感じるかもしれません。
大切なのは、まず一般的な「相場」を知り、その上で提示された価格の「裏側」にある理由を考えることです。
ホームページ制作の費用は、作るサイトの種類や規模、依頼先(制作会社かフリーランスか)によって大きく変わります。
ざっくりとした目安ですが、
- 簡単な数ページのサイト(個人事業主や小規模店舗向け): 10万円~50万円程度
- 一般的なコーポレートサイトやサービスサイト(中小企業向け): 50万円~150万円程度
- ECサイトや大規模なシステム連携が必要なサイト: 150万円~数百万円以上
といった感じでしょうか。
フリーランスに依頼すれば、これより安くなる傾向があります。
僕自身も「29ホームページ」として、3ページまで29,000円、10ページまで59,000円という格安で提供していますが、これはWordPressとSWELLという優れたテーマを使い、効率化を図ることで実現している価格です。
もし、相場と比べて極端に「安い」見積もりが出てきた場合、その裏には次のような理由が隠れている可能性があります。
- テンプレートデザインをほぼそのまま使うため、オリジナリティが出せない。
- 見積もりに含まれる作業範囲が非常に限定的で、後から追加費用がたくさん発生する。
- サポート体制が整っておらず、公開後のフォローが期待できない。
- 実は経験の浅い制作者が担当する。
逆に、極端に「高い」見積もりの場合は、
- 完全オーダーメイドで、デザインや機能に非常にこだわっている。
- SEO対策やWebマーケティング戦略の立案・実行まで含まれている。
- 保守・運用サポートが非常に手厚い。
といった理由が考えられます。
価格が高いか安いかだけでなく、「その価格でどんな価値を提供してくれるのか?」を見極めることが重要なんです。
見積もり金額に疑問を感じたら、



この価格にはどのような作業が含まれていますか?
と、正直に聞いてみましょう。
その回答の内容や丁寧さも、業者さんを見極めるヒントになりますよ。
こんな見積もり・提案は要注意!危険サインの見分け方リスト
残念ながら、中にはあまり誠実とは言えない業者さんも存在します…。
そういった業者さんが出してくる見積もりや提案には、いくつか共通した「危険サイン」が見られることが多いんです。
事前にこれらのサインを知っておけば、



あれ、この業者さん、ちょっと怪しいかも?
と気づき、トラブルを未然に防げます。
ぜひ、以下のチェックリストを参考に、見積もりや提案内容、そして担当者の対応を注意深く見てみてください。
- 見積もりの内訳が大雑把すぎる
「ホームページ制作一式 〇〇円」のような表記が多く、具体的な作業内容が不明瞭。何が含まれていて何が含まれていないのか分からない。 - 価格が相場から極端に乖離している
異常に安い、または異常に高い。その理由について、納得のいく説明がない。 - 契約を異常に急かす
「今すぐ契約しないとこの価格は適用できません!」「キャンペーンは今日までです!」などと、考える時間を与えずに契約を迫る。 - 質問への回答が曖昧
具体的な質問をしても、「大丈夫です」「上手くやります」といった曖昧な返答しかしない。専門用語で煙に巻こうとする。 - 初期費用が異常に安いが、月額費用や保守費用が高額
トータルコストで見ると、結局高くつくケース。 - メリットばかり強調し、デメリットやリスクの説明がない
良いことしか言わず、都合の悪い情報(追加費用の可能性、できないことなど)を隠そうとする。 - 打ち合わせでの担当者の態度
こちらの話をしっかり聞かない。態度が横柄。専門用語を多用して、こちらが理解しているか確認しない。 - 制作実績の提示を渋る、または実績が疑わしい
具体的な制作事例を見せてくれない。見せてくれても、本当にその会社が作ったのか疑わしい(デザインが古すぎる、内容が薄いなど)。 - 連絡が取りにくい
問い合わせへの返信が極端に遅い。担当者が頻繁に変わる。
もし、これらのサインに複数当てはまるようなら、その業者さんとの契約は慎重に考えた方が良いかもしれませんね…。
少しでも「おかしいな?」と感じたら、立ち止まって冷静に判断する勇気も大切です。
信頼できる制作会社選びのポイント【実績・担当者を確認】
では、逆に「信頼できる制作会社」はどうやって見つければ良いのでしょうか?
僕がフリーランスとして活動する上で大切にしていること、そしてお客様の立場から見ても重要だと思うポイントは、大きく分けて「実績」と「担当者」の2つです。
まず「実績」について
実績は、その制作会社がこれまでどんなホームページを作ってきたのか、その実力を示す最も分かりやすい指標です。
以下の点を確認してみましょう。
- 実績の数と質
どれくらいの数のホームページを作ってきたか? デザインのクオリティはどうか? 使いやすそうか? - 自社の業種や目的に近い実績
あなたが作りたいホームページと似たような実績があるか? 例えば、飲食店なら飲食店のサイト、士業なら士業のサイトの実績があると、話がスムーズに進みやすいです。 - 実際のサイトを確認
ポートフォリオに載っている画像だけでなく、実際にそのホームページにアクセスして、動きや表示速度なども確認してみると良いでしょう。
「担当者」について
実績と同じくらい重要なのが「担当者」です。
ホームページ制作は、依頼主と制作担当者が協力して進めるプロジェクトです。
担当者との相性やコミュニケーションの質が、プロジェクトの成功を大きく左右すると言っても過言ではありません。
以下の点に注目してみてください。
- コミュニケーションのしやすさ
あなたの話を親身になって聞いてくれるか? 専門用語を分かりやすく説明してくれるか? - レスポンスの速さと誠実さ
質問や相談に対する返信は早いか? 丁寧に対応してくれるか? - 提案力
あなたの目的や要望を深く理解した上で、具体的な提案をしてくれるか? その提案に納得できる根拠はあるか? - 人柄・相性
「この人になら安心して任せられそうだな」「一緒に良いものを作っていけそうだな」と感じられるか? 最後は直感も意外と大事だったりします。
どんなに実績が素晴らしくても、担当者とのコミュニケーションが上手くいかなければ、ストレスが溜まってしまいます。
見積もりの内容だけでなく、これらの点も総合的に判断して、あなたにとって最高のパートナーを見つけてください!
相見積もりを有効活用!比較検討で納得の依頼先を見つけるコツ



どの制作会社に頼めば良いか分からない…



提示された見積もりが妥当なのか判断できない…
そんな時に非常に有効なのが、「相見積もり(あいみつもり)」を取ることです。
相見積もりとは、複数の制作会社さんに同じ条件で見積もりを依頼し、その内容を比較検討すること。
相見積もりには、たくさんのメリットがあるんですよ。
- 適正な相場感がつかめる
1社だけだと高いのか安いのか分かりませんが、複数社比較することで、おおよその相場が見えてきます。 - 提案内容の違いが分かる
各社がどんな強みを持っていて、どんなアプローチであなたの要望を叶えようとしてくれるのか、その違いが明確になります。 - 担当者との相性を比較できる
打ち合わせなどを通して、どの会社の担当者と一番コミュニケーションが取りやすいか、信頼できそうかを比較できます。 - より良い条件を引き出せる可能性も
各社の提案内容を比較することで、価格やサービス内容について、より有利な条件で契約できる可能性も出てきます。(ただし、値切ることだけが目的にならないように注意しましょうね!)
では、何社くらいから相見積もりを取るのが良いのでしょうか?
一般的には、3社程度が目安と言われています。



あまり多すぎると、比較検討するだけで疲れてしまいますからね…。
相見積もりを依頼する際の重要なコツは、「全ての会社に同じ条件(目的、予算、必須機能など)を伝えること」です。
条件がバラバラだと、見積もり内容もバラバラになってしまい、正しく比較することができません。
そして、各社から見積もりが出揃ったら、以下のポイントでじっくり比較検討しましょう。
- 金額
単純な総額だけでなく、内訳、作業範囲、追加費用の条件などを比較。 - 提案内容
あなたの目的や要望をどれだけ理解し、具体的な解決策を提案してくれているか? - 実績
あなたが作りたいサイトに近い実績があるか? クオリティはどうか? - 担当者の対応
コミュニケーションはスムーズか? 信頼できそうか? - 契約条件
著作権の帰属、保守・運用の内容など、不利な条件はないか?
重視するポイントは、あなたの状況に合わせて変わるはずです。
例えば、



デザインの自由度や担当者との相性を重視しよう



実績や提案力、費用対効果が大切!
このように、ご自身の状況に合わせて優先順位をつけて、見積もり内容を比較すると良いでしょう。
手間はかかりますが、相見積もりをしっかり行うことで、後悔のない、納得のいく依頼先を見つけることができますよ!
ホームページ見積もりのギモン解決!よくある質問【FAQ】
ここまで、ホームページ制作の見積もりに関する注意点やチェックポイントを詳しく見てきましたね。
でも、もしかしたら、「他にも細かいことで分からないことがあるんだけど…」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
そこでこの最後の章では、ホームページ制作の見積もりに関して、特によく聞かれる質問とその回答をQ&A形式でまとめてみました!
皆さんが抱えがちな疑問をスッキリ解消して、安心してホームページ制作を進めるためのお手伝いができれば嬉しいです。



それでは、早速見ていきましょう!
サイトの種類別!ホームページ制作費用の相場はいくらくらい?
これは、本当によく聞かれる質問No.1かもしれませんね!
「ズバリ、いくらくらいかかるの?」って、やっぱり気になりますよね。
ただ、正直にお答えすると、「ホームページ制作の費用は、〇〇円です!」と一概に言うのは非常に難しいんです…。
なぜなら、作るホームページの種類、規模(ページ数)、必要な機能、デザインへのこだわり具合、そして依頼先(制作会社か、僕のようなフリーランスか)など、様々な要因で価格が大きく変動するからです。
とはいえ、全く目安がないと困ってしまいますよね。
そこで、あくまで一般的な「相場観」として、サイトの種類別にざっくりとした費用感をお伝えしますね。
| サイトの種類 | 費用の目安 (制作会社) | 費用の目安 (フリーランス) | 主な目的・特徴 |
|---|---|---|---|
| 個人ブログ 小規模サイト | 10万円~30万円 | 数万円~20万円 | 個人の情報発信、簡単な紹介。機能は少なめ。 |
| 店舗 個人事業主サイト | 30万円~80万円 | 10万円~50万円 | お店の紹介、サービス案内、予約機能など。 |
| コーポレートサイト | 50万円~150万円 | 30万円~100万円 | 会社の信頼性向上、情報提供、採用活動など。 |
| ポートフォリオサイト | 30万円~100万円 | 10万円~70万円 | 作品紹介、ブランディング。デザイン性が重視されることが多い。 |
| サービスサイト LP | 50万円~200万円 | 20万円~120万円 | 特定の商品・サービスの紹介、集客、問い合わせ獲得。 |
| ECサイト (ネットショップ) | 100万円~数百万円以上 | 50万円~数百万円 | 商品販売、決済機能、在庫管理など。機能が複雑になりがち。 |
※あくまで目安であり、実際の費用は要件によって大きく異なります。
フリーランスの場合、制作会社よりも費用を抑えられる傾向があります。
僕自身も「29ホームページ」として格安プランを提供していますが、これはWordPressテーマ「SWELL」を活用したり、効率的な制作フローを確立したりすることで実現しています。
見積もりは何社から取るのがベスト?目安はありますか?
「見積もりは、1社だけじゃなくて複数から取った方が良いって聞くけど、実際、何社くらいに頼むのが一番良いの?」という疑問もよくありますね。
結論から言うと、最低でも3社程度から相見積もりを取ることを強くおすすめします!
なぜ3社なのか?
理由はいくつかあります。
- 比較対象ができる
1社だけだと、その見積もりが妥当なのか、他により良い提案がないのか分かりません。2社だと「安すぎたり」「高すぎたり」両極端になってあなたに合う制作会社が見つけれないことも。3社あれば、それぞれの特徴や価格帯を比較しやすくなります。 - 適正な相場感が掴める
3社程度の見積もりを比較すれば、大体の相場感が見えてきます。極端に高い、あるいは安い見積もりがあれば、その理由を確認するきっかけにもなります。 - 提案内容や担当者を比較できる
価格だけでなく、各社がどんな提案をしてくれるのか、担当者とのコミュニケーションはスムーズか、といった「質」の部分もしっかり比較できます。
もちろん、時間と労力に余裕があれば、4社、5社と見積もりを取ることも可能です。
ただ、あまり多くなりすぎると、各社とのやり取りや比較検討が大変になり、かえって判断が難しくなってしまうことも…。
ですから、まずは「3社」を目安にするのが現実的で、かつ効果的なラインだと僕は考えています。



相見積もりを依頼する際は、必ず全ての会社に同じ条件(目的、予算、要望など)を伝えるようにしてくださいね。
そうしないと、公平な比較ができませんから。
手間は少しかかりますが、このひと手間が、あなたにとって最高のパートナーを見つけるための近道になりますよ!
見積もり後の値引き交渉、どう進めるのが賢い方法?
「提示された見積もり、ちょっと予算オーバーだな…もう少し安くならないかな?」
そんな風に思うこと、ありますよね。
特に、「限られた予算の中で最大限の効果を出したい」と考えている方や、「費用対効果をシビアに見ている方」にとっては、切実な問題かもしれません。
では、見積もり後の「値引き交渉」は可能なのでしょうか?
答えは、「交渉自体は可能ですが、やり方には注意が必要」です。
単に「もっと安くしてください!」とストレートにお願いするだけでは、あまり良い結果に繋がらないことが多いかもしれません。
最悪の場合、制作会社さんとの関係が悪化してしまったり、「じゃあ、この機能を削りますね」と品質が下がってしまったりする可能性もあります…。
僕がおすすめする「賢い交渉の進め方」は、一方的な値引き要求ではなく、お互いが納得できる着地点を探る建設的なアプローチです。
具体的には、以下のような方法を試してみてはいかがでしょうか。
- 予算を正直に伝えて相談する
「予算が〇〇円なのですが、この金額内で実現するために、何か調整できる部分はありますでしょうか?」と相談してみる。 - 機能や仕様を見直す
「この機能は必須ではないので、削ることは可能ですか?」「デザインはもう少しシンプルなものでも大丈夫です」など、要望の優先順位を見直し、コストダウンに繋がる提案をしてみる。 - 作業範囲を調整する
「原稿作成や写真素材の準備はこちらで行うので、その分費用を調整できませんか?」など、自分でできる作業を申し出てみる。
制作会社さんもプロですから、無理な値引き要求には応えられないこともあります。
お互いに気持ちよくプロジェクトを進めるためにも、一方的な要求ではなく、協力して解決策を探る姿勢を持つことが大切ですよ。
保守・運用費用って何?契約前に確認すべきこととは?
「ホームページが完成したら、それで終わりじゃないの?」「保守・運用費用って、何にかかるお金なの?」
これも、初めてホームページを作る方には分かりにくい点かもしれませんね。
先ほども少し触れましたが、ホームページは公開した後も、安定して安全に動かし続けるために、定期的なメンテナンスが必要なんです。
このメンテナンスにかかる費用が「保守・運用費用」と呼ばれるものです。
具体的に、保守・運用にはどのような内容が含まれることが多いのでしょうか?
主なものとしては、以下のような項目が挙げられます。
- サーバー・ドメインの管理・費用
ホームページを置いておく場所(サーバー)のレンタル代や、ホームページのアドレス(ドメイン)の維持費です。これらは通常、年単位や月単位で費用が発生します。 - CMSやプラグインのアップデート
WordPressなどのシステムを使っている場合、セキュリティ強化や機能改善のために、定期的にソフトウェアを最新版に更新する必要があります。 - セキュリティ対策
不正アクセスやウイルス感染、サイト改ざんなどを防ぐための監視や対策です。 - 定期的なバックアップ
万が一、データが消えてしまったり、サイトに問題が発生したりした場合に備えて、定期的にサイトのデータを保存(バックアップ)しておく作業です。 - 簡単な更新・修正作業のサポート
電話やメールでの質問対応、軽微なテキスト修正や画像の差し替えなどを、一定の範囲内で対応してくれるサービスです。(どこまで対応してくれるかは、契約内容によります)
これらの保守・運用作業は、専門知識がないと難しかったり、時間がかかったりすることが多いです。
そのため、制作会社さんに有料で依頼するケースが一般的です(もちろん、自分で全て管理するという選択肢もあります)。
保守・運用については、ホームページ制作の見積もりとは別に、「保守契約」として提案されることが多いです。
契約前には、以下の点をしっかり確認しましょう。
- サポート範囲
どの作業まで対応してくれるのか? 対応してくれる作業の頻度や上限(例:月〇時間まで)は? - 費用
月額いくらかかるのか? 年額か? 費用に含まれるもの、含まれないものは何か? - 対応時間
いつ、どのように連絡すれば対応してくれるのか?(平日日中のみ、メールのみ、など) 緊急時の対応は? - 契約期間と更新
契約期間は? 自動更新なのか? 解約する場合の手続きは?
特に、「ITにあまり詳しくない方」や、「サイトの安定稼働やセキュリティを重視する方」は、保守契約の内容をしっかり確認し、ご自身の状況に合ったプランを選ぶことが大切です。



「作って終わり」ではなく、長期的な視点でホームページの運用を考えておくことが、その価値を最大限に引き出すことに繋がりますよ
まとめ:HP見積もりの不安解消!3つの確認で失敗は防げます
今回は、ホームページ制作の見積もりで失敗したくない、不安を感じている方に向けて、
- 見積もり依頼前にやるべき準備の大切さ
- 見積書の項目別チェックポイントと注意点
- 怪しい業者や危険な見積もりの見分け方
上記について、WordPressを使ったホームページ制作者としての筆者の経験も交えながらお話してきました。
少しの手間で大きな失敗を防げますから、疑問点は遠慮なく質問してみてくださいね。
あなたのホームページ作り、心から応援しています!