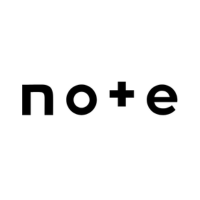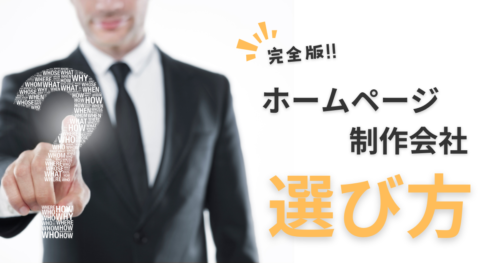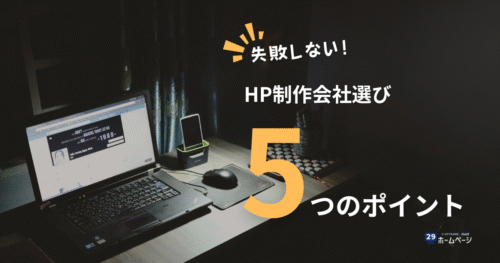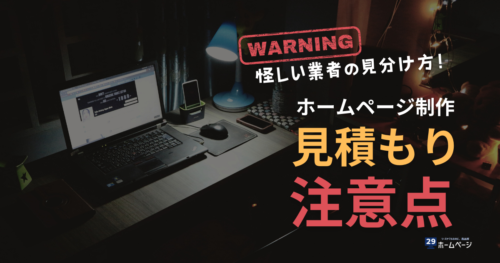ホームページ制作会社の選び方|制作者が教える【3つの必須確認点】
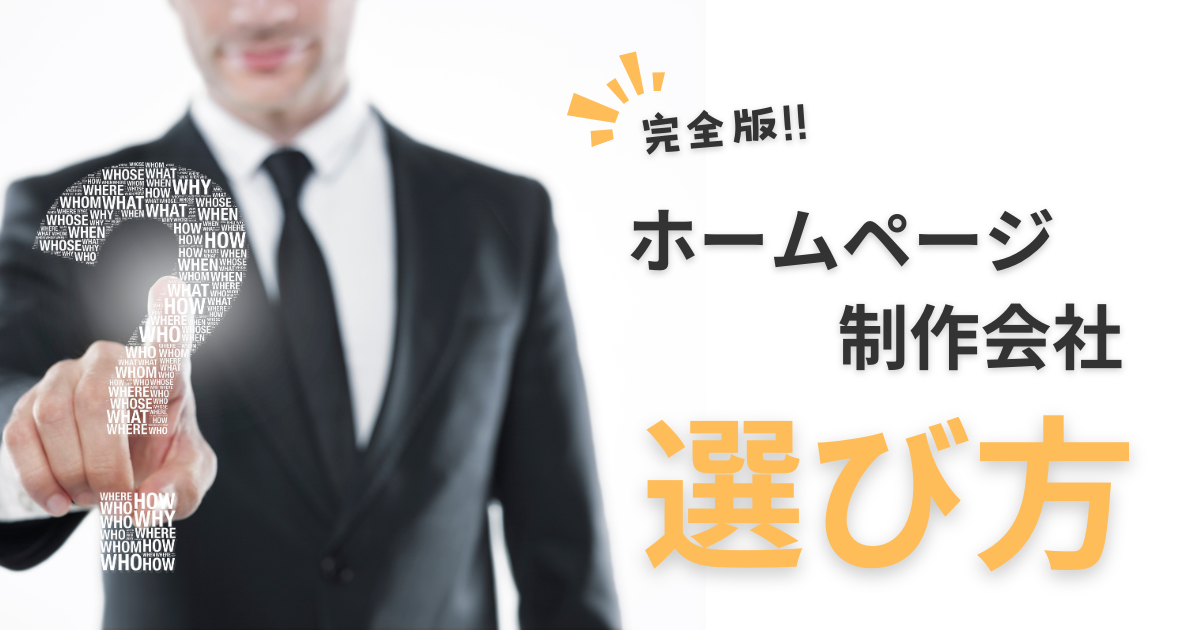
ホームページを作りたいけど、「たくさん会社があって、どこを選べばいいのか分からない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ホームページ制作会社選びって、本当に迷いますよね。
 筆者
筆者僕がHP制作者として、色々な会社を調べていく中で痛感したのは、次のことです
この記事では、「納得できるホームページ制作会社を選びたいと考えている方」に向けて、
- ホームページを作る「目的」を明確にする方法
- 失敗しないための3つの最重要チェックポイント
- 具体的な制作会社の選定ステップと流れ
- 後悔しないための費用相場と見積もりの見方
上記について、現役のホームページ制作者である僕自身の経験も交えながら、分かりやすく解説します。
ぜひ参考にして、あなたにピッタリの会社を見つけ、ビジネスを加速させるホームページを手に入れてください!
ホームページ制作会社の選び方
ホームページ制作会社の選び方、本当に迷いますよね…。
僕も「ホームページ制作サービス」を始めるために色々と調べた経験からも



良い制作会社を見つけるのって大変だな・・・
と感じています。
でも、大丈夫ですよ!
失敗しないためには、いくつか大事なポイントがあるんです。
この記事で詳しくお話ししますが、特に「なぜホームページが必要なのか?」という目的をしっかり持つことが、良い会社選びの第一歩になります。
なぜ慎重な「HP制作会社選び」が、あなたのビジネスに重要なのか?
そもそも、なぜホームページ制作会社を慎重に選ぶ必要があるのでしょうか?
それは、ホームページは、あなたのビジネスを成長させるための大切な「投資」だからです。
僕も最初は



とにかく安く作れれば良いのかな…
なんて考えていた時期もありました。
でも、実際に制作に関わるようになってみて痛感したのは、目的とズレたホームページを作ってしまうと、時間もお金も無駄になりかねないということです…。
これでは、投資した意味がなくなってしまいますよね。
だからこそ、あなたのビジネスの目的達成を真剣に考えてくれる、信頼できるパートナーを慎重に選ぶことが、本当に重要になってくるのです。
ホームページ制作でよくある失敗パターンとその回避策
慎重に選ぶべき、とは言っても、



具体的にどんな失敗があるの?
と気になりますよね。
僕が制作者として見聞きしてきた中で、「あー、それはもったいない…」と感じる失敗パターンがいくつかあります。
でも安心してください!
失敗のパターンを知っておけば、事前に対策を打つことができますよ。



よくある失敗パターンと、その簡単な回避策をいくつか挙げてみますね
- 失敗1:価格の安さだけで選んでしまう
回避策:安さだけで飛びつかず、見積もり内容(どこまで含まれるか)や実績、サポート内容をしっかり確認しましょう。費用対効果で考えることが大切です。 - 失敗2:ホームページを作る目的が曖昧なまま依頼してしまう
回避策:次の章でお伝えしますが、まず「なぜ作るのか」「何を達成したいのか」を明確にしてから、会社探しを始めましょう。これが無いと、会社側も最適な提案ができません。 - 失敗3:制作実績(ポートフォリオ)を雰囲気だけで見てしまう
回避策:デザインの好みだけでなく、「自分の業種に近いか」「似たような目的のサイトがあるか」「成果は出ているか(可能なら確認)」という視点で実績をチェックすることが重要です。 - 失敗4:制作会社に「丸投げ」してしまう
回避策:いくらプロでも、あなたのビジネスのことを一番理解しているのはあなた自身です。任せっきりにせず、積極的に要望を伝え、確認作業にも協力する姿勢が大切になります。 - 失敗5:担当者とのコミュニケーションがうまくいかない
回避策:問い合わせ時の対応や打ち合わせで、「話しやすいか」「こちらの意図を汲み取ってくれるか」「専門用語ばかりでなく、丁寧に説明してくれるか」などを確認しましょう。相性は意外なほど大事です! - 失敗6:公開後の保守・運用について確認しない
回避策:ホームページは作って終わりではありません。更新や修正、サーバー管理など、公開後のサポート範囲と費用を契約前に必ず確認しておきましょう。
これらの点を意識するだけでも、失敗のリスクはぐっと減らせるはずです。
まずはココから!ホームページを作る「目的」を明確にしよう
さて、失敗パターンを知っていただいたところで、いよいよ会社選び…の前に!
僕が、



これが一番大事!
と、考えているステップがあります。
それは、あなた自身が「なぜホームページを作りたいのか?」そして「ホームページで何を達成したいのか?」という『目的』を、できるだけ具体的にすることです。
ここがしっかり固まっていないと、どんなに評判の良い制作会社を選んだとしても、



なんだか思っていたのと違う…
という結果になりかねません。
逆に目的が明確なら、それに合った会社を選びやすくなりますし、制作会社側も的確な提案をしやすくなるんですよ。
あなたのビジネス課題は?ホームページで達成したいゴール設定



目的を明確にするって、具体的にどうすればいいの?
と、思われるかもしれませんね。
難しく考える必要はありませんよ!
まずは、あなたのビジネスが今抱えている「課題」や「悩み」を書き出してみるのがおすすめです。
そして、その課題を解決するために、ホームページがどんな役割を果たせたら嬉しいかを考えてみてください。



例えば、以下のような感じです
- 「もっと新しいお客さんに知ってもらいたい!」
→ ゴール:新規顧客からの問い合わせを月〇件獲得する - 「お店やサービスの信頼感を高めたい!」
→ ゴール:お客様の声や実績を掲載し、安心感を与える - 「採用活動を強化したい!」
→ ゴール:会社の魅力や働きがいを伝え、求人応募数を増やす - 「予約や問い合わせ対応の手間を減らしたい!」
→ ゴール:予約システムやFAQを導入し、業務を効率化する - 「自分の専門性や実績をしっかり伝えたい!」(フリーランスの方など)
→ ゴール:ポートフォリオサイトでブランディングし、高単価の案件を獲得する
このように、「現状の課題」と「ホームページで達成したいゴール(理想の状態)」を結びつけて言葉にしてみましょう。
可能であれば、「問い合わせ数を〇%増やす」「売上を〇万円アップさせる」のように、具体的な数値目標を設定できると、さらに効果測定がしやすくなります。
このゴール設定が、制作会社選びの最も重要な「軸」になるんです。
誰に届けたい?ターゲットを具体的にイメージする
目的とゴールが見えてきたら、次に考えてほしいのが、そのホームページを「誰に届けたいのか?」ということです。
つまり、あなたのホームページの「ターゲット」は誰なのか、具体的にイメージするんですね。



そんなの考えたことない…
という方もいるかもしれませんが、大丈夫です!
まずは、あなたの理想のお客さんや、これまでに関わった中で印象に残っているお客さんなど、たった一人でも良いので顔を思い浮かべてみてください。
その人は、どんなことに悩んでいて、どんな情報を探しているでしょうか?
どんな言葉やデザインに興味を持つでしょうか?



ターゲットを具体的にイメージすることで、以下のことが明確になってきます!
- どんなデザインテイストが良いか?
(例:若者向けならポップに、経営者向けなら信頼感のあるデザインに) - どんな情報を載せるべきか?
(例:初心者向けには基礎知識から、専門家向けには詳細なデータを) - どんな言葉遣いで語りかけるべきか?
(例:親しみやすく、専門的に、など) - どんな機能が必要か?
(例:簡単な問い合わせフォーム、高機能な予約システム、など)
ターゲット像が具体的であればあるほど、制作会社も



この人には、こういう見せ方や機能が必要ですね!
と、より的確な提案がしやすくなります。
まずは「この人に届けたい!」という気持ちを大切に、具体的な人物像を描いてみてくださいね。
ちなみにこの作業を「ペルソナ設定」と言いますよ。
どんな種類がある?ホームページ制作会社の特徴を知っておこう
ホームページを作る目的とターゲット(ペルソナ)が明確になったら、いよいよ制作パートナー探しです。



「制作会社」と一口に言っても、実は色々なタイプがあるんですよ
例えば、大きな会社もあれば、僕のようなフリーランスもいますし、得意な分野も様々です。
それぞれの特徴を知っておくと、



私の場合は、こういう相手が合いそうだな!
という当たりをつけやすくなります。
まずは、どんな種類の制作パートナーがいるのか、全体像を把握しておきましょう!
制作会社 vsフリーランス:メリット・デメリット比較
ホームページ制作の依頼先として、まず大きく分けられるのが「制作会社」と「フリーランス(個人事業主)」です。



僕自身もフリーランスとして活動していますが、どちらが良い・悪いということではなく、それぞれに得意なことや、ちょっと注意が必要な点があると感じています
「結局、どっちに頼むのがいいの?」と迷われる方も多いと思うので、それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。
制作会社とフリーランスの比較
| 比較ポイント | 制作会社 | フリーランス |
|---|---|---|
| 料金 | 比較的高め | 比較的安価 |
| 品質・信頼性 | 比較的安定、実績豊富 | ばらつきあり、見極め重要 |
| スピード・柔軟性 | 分業体制で遅れることも、ルールが厳しい場合あり | 比較的速い、小回りが利く |
| 対応範囲 | デザイン・開発・マーケ等、総合的に対応可 | 得意分野が限定的な場合あり |
| コミュニケーション | 分業による伝達ロスや、担当者変更の可能性がある | 直接制作者とやり取りできる |
| サポート体制 | 継続的な保守・運用体制が整っていることが多い | 対応は人による、継続性に不安がある場合も |
制作会社のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 複数人体制で分業していることが多く、品質が安定しやすい デザイン、システム、マーケティングなど幅広い対応が可能 会社としての信頼性や継続的なサポート体制が期待できる | 人件費やオフィス経費がかかるため、料金は高くなる傾向 分業による伝達ロスや、担当者変更の可能性も ルールがしっかりしている分、小回りが利きにくい場合がある |
フリーランスのメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| コストを抑えられるため、料金が比較的安い 制作者本人と直接やり取りできるため、コミュニケーションがスムーズ 柔軟な対応やスピード感に期待できる | スキルや経験、信頼性に個人差が大きい 一人で対応できる範囲が限られる場合がある 病気や廃業などで、継続的なサポートが難しくなるリスクも |
どちらを選ぶかは、あなたの予算、求めるホームページの規模や品質、重視するポイント(価格、スピード、信頼性、サポートなど)によって変わってきます。



一概にどちらが良いとは言えないので、それぞれの特徴を理解した上で、ご自身の状況に合わせて検討してみてくださいね
デザイン特化、システム開発、マーケティング支援…得意分野で選ぶ視点
制作会社やフリーランスの中にも、さらに「得意分野」があります。
例えば、以下のような得意分野を持つ会社・人がいます。
- デザイン特化型
見た目の美しさ、ブランドイメージの表現、UI/UX(使いやすさ)のデザインに強みを持つ。クリエイティブな業種や、デザイン性を重視するサイトに向いています。 - システム開発特化型
複雑な機能(予約システム、会員機能、データベース連携など)の実装や、Webアプリケーション開発が得意。機能性を重視するサイトや、業務システム連携が必要な場合に頼りになります。 - マーケティング支援(SEO・集客)特化型
ホームページを作るだけでなく、その後の集客(SEO対策、Web広告運用、コンテンツマーケティングなど)まで見据えた提案や施策が得意。集客や売上アップを最重要視する場合におすすめです。 - 業種特化型
特定の業界(例:医療、不動産、飲食など)の専門知識や制作実績が豊富。業界特有の慣習や必要な機能を理解しているため、話が早く、効果的なサイトを作りやすい。 - 小規模・個人向け特化型
中小企業や個人事業主、店舗などの比較的小規模なサイト制作をメインにしている。リーズナブルな価格設定や、初心者にも分かりやすい説明、丁寧なサポートが期待できることが多いです。
(僕もここに当てはまります!)
あなたのホームページの「目的」を達成するためには、どの分野の強みが必要かを考えてみましょう。
そして、候補となる会社やフリーランスの実績(ポートフォリオ)を見たり、打ち合わせで話を聞いたりする中で、



この人は、自分の目的に合った強みを持っているか?
という視点で確認することが大切です。



得意分野がマッチする相手を選ぶことが、ホームページ制作成功への近道ですよ
個人事業主が依頼する場合のポイント
この記事を読んでくださっている方の中には、僕と同じように個人事業主やフリーランスとして活動されている方も多いのではないでしょうか。
個人事業主の方がホームページ制作を依頼する場合、



会社員の方とは少し違った視点や注意点があるな・・・
と、僕自身の経験からも感じています。
限られた資金の中で、できるだけ効果の高い、そして長く使えるホームページを作りたいですよね。
僕も個人事業主なので、その気持ち、よくわかります!
そんな個人事業主の方が制作パートナーを選ぶ際に、特に意識してほしいポイントをまとめました。
- 費用対効果をシビアに見る
限られた予算の中で最大の効果を得たいですよね。初期費用だけでなく、月額費用や更新費用など、トータルでかかるコストと、それによって得られる効果(集客、効率化など)をしっかり比較検討しましょう。「安かろう悪かろう」は避けたいですが、高ければ良いというものでもありません。 - 自分で更新・運用しやすいか
外部に更新を頼むとコストがかさむことも。ブログ投稿や簡単なテキスト修正、スケジュール更新など、自分でできる範囲を広げられるような作り(例えばWordPressのようなCMS導入)や、更新方法のレクチャーがあるかを確認しましょう。 - コミュニケーションの取りやすさ
大きな組織だと担当者が細分化されていて話が進みにくいことも。個人事業主の場合、制作者と直接、気軽に相談できる関係性が築けると心強いです。専門用語を並べるのではなく、こちらの状況を理解し、分かりやすく説明してくれるかも重要ですね。 - 「丸投げ」ではなく「協働」できるか
あなたのビジネスの強みや想いを一番知っているのは、あなた自身です。制作パートナーにそれをしっかり伝え、一緒に作り上げていく意識を持つことが大切です。あなたの想いをしっかりヒアリングしてくれる相手を選びましょう。 - スモールスタートも視野に
最初から完璧を目指さず、まずは必要最低限の機能でスタートし、ビジネスの成長に合わせて拡張していく、という考え方も有効です。柔軟に対応してくれる相手かどうかも確認ポイントです。



個人事業主の状況を理解し、親身になって相談に乗ってくれる、信頼できるパートナーを見つけることが、何より大切だと思います!
【最重要】失敗しない制作会社選び!ニックが考える3つのポイント
さて、ここまでホームページを作る目的や制作会社の種類についてお話ししてきました。
いよいよ「具体的にどうやって制作会社を選んでいけば良いのか」という本題に入っていきましょう!
色々な比較ポイントがありますが、僕がこれまでの経験や調査を通して



ここだけは絶対に押さえてほしい!
と強く感じている、特に重要なポイントが3つあります。
それは、ズバリこの3点です!
- あなたの「目的達成」に本気で向き合ってくれるか?
- 「制作実績」は、あなたの目的や業種と合っているか?
- 担当者との「相性」やコミュニケーションはスムーズか?
上記3つの視点をしっかり持っていれば、きっとあなたにとって最適なパートナーが見つかるはずです。
それぞれのポイントについて、詳しく説明していきますね。
ポイント1:あなたの「目的達成」に本気で向き合ってくれるか?
まず最初の、そして僕が最も重要だと考えているポイントが、「あなたのホームページを作る目的の達成に、本気で向き合ってくれるか?」どうかです。
思い出してください、ホームページは「作る」ことがゴールではなく、その先にある「目的(集客、ブランディング、業務効率化など)」を達成するための「手段」でしたよね。
だから、単に「言われたものを作ります」という姿勢の会社ではなく、「どうすればその目的を達成できるか?」を一緒に考え、提案してくれる会社を選ぶことが大切なんです。



でも、本気度ってどうやって見極めるの?
そう思いますよね。
一番分かりやすいのは、最初のヒアリング(打ち合わせ)の時です。
あなたのビジネスや、ホームページを作りたい理由について、どれだけ深く質問してくれるかを見てみてください。



例えば、以下のような質問を具体的にしてくれる会社は、目的達成を意識している可能性が高いと言えるでしょう!
- 「今回ホームページを作ろうと思われたきっかけは何ですか?」
- 「ホームページを通じて、具体的にどのような成果(例:問い合わせ数、売上など)を目指したいですか?」
- 「ターゲットとなるお客様は、どのような方々でしょうか?」
- 「現在、ビジネスで抱えている課題は何ですか?」
- 「競合となる会社やサービスはありますか?その違いは何でしょうか?」
もし、こうした質問があまりなく、すぐにデザインや機能の話ばかりになるようなら、少し注意が必要かもしれません…。
もちろん、素晴らしい技術を持っている会社かもしれませんが、あなたの「目的達成」という視点が抜けている可能性があるからです。
あなたのビジネスの成功を、まるで自分のことのように考えてくれる。
そんな熱意と誠実さを持ったパートナーを見つけられるかどうかが、ホームページ制作の成否を決める、最初の大きな分かれ道になります。
ポイント2:「制作実績」で見逃せないチェック項目とは?【事例の見方】
次に重要なのが、「制作実績(ポートフォリオ)」のチェックです。
ほとんどの制作会社は、自社のウェブサイトに過去に手掛けたホームページの事例を掲載しています。
これを見ることで、その会社のデザインのテイストや技術力を知ることができます。



わぁ、このデザイン素敵!
と感じることはもちろん大切です。
でも、それだけで判断してしまうのは、ちょっと待ってください!
実績を見る際には、デザインの好み以外にも、いくつかチェックしてほしい項目があるんです。



僕が特に重要だと思うチェック項目は、以下の通りです
- あなたの業種やビジネスに近い実績があるか?
全く違う業種のデザインばかりだと、あなたのビジネスの特性やターゲット層を理解してもらうのに時間がかかるかもしれません。同業種や類似業種の実績があれば、話がスムーズに進みやすいでしょう。 - あなたのホームページの目的に近い実績があるか?
例えば、あなたが「集客」を目的としているなら、同じように集客目的で作られたサイトの実績があるか。あなたが「ブランディング」を重視するなら、ブランドイメージを効果的に伝えているサイトの実績があるか、といった視点です。 - デザインだけでなく、機能性や使いやすさはどうか?
見た目が良くても、情報が探しにくかったり、操作が分かりにくかったりしては、ホームページの効果は薄いですよね。実際に実績サイトを操作してみて、ユーザー視点での使いやすさ(UI/UX)も確認してみましょう。 - 成果に繋がっていそうか?(可能であれば)
制作会社によっては、「このサイトを作った結果、問い合わせが〇倍になりました!」といった成果を記載している場合もあります。もし記載があれば、非常に参考になりますね。(もちろん、全ての会社が載せているわけではありません) - 更新性や拡張性は考慮されていそうか?
特にブログ機能や、後からページを追加する可能性がある場合、更新しやすい仕組み(CMS導入など)で作られているか、実績から推測できる部分もあります。
これらの点を意識して制作実績を見ることで、単なる「好き嫌い」だけでなく、



私の目的達成に貢献してくれそうかな?
という、より本質的な視点で制作会社を評価できるようになります。
ポイント3:意外と見落としがち?担当者との「相性」とコミュニケーション
最後のポイントは、意外と見落とされがちですが、実は非常に重要な「担当者との相性」と「コミュニケーションの質」です。
ホームページ制作は、数ヶ月にわたる共同作業になることも少なくありません。
その間、何度も打ち合わせを重ね、メール、チャット、電話などでやり取りをすることになります。
そのため、担当してくれる方と気持ちよく、スムーズにコミュニケーションが取れるかどうかは、プロジェクトの成否を左右すると言っても過言ではないんです。



僕も制作者として、「このお客さんとは、すごくやりやすかったな」と感じる時もあれば、「うーん、ちょっと意思疎通が難しいな…」と感じる時も正直あります…。
これは、どちらが良い・悪いという話ではなく、単純に「相性」の問題が大きいと思っています。
では、どうやって相性やコミュニケーションの質を見極めれば良いのでしょうか?
問い合わせ時の対応や、最初の打ち合わせでの印象が大きなヒントになります。



以下の点をチェックしてみてください
- 話しやすい雰囲気か?質問しやすいか?
威圧的だったり、専門用語ばかりでこちらの話を聞いてくれなかったりすると、不安になりますよね。「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思わずに、気軽に質問できる雰囲気があるかは重要です。 - こちらの意図を丁寧に汲み取ろうとしてくれるか?
専門知識がないこちらの話を根気強く聞き、意図を正確に理解しようと努めてくれる姿勢があるかを見てみましょう。 - 説明は分かりやすいか?専門用語を使いすぎていないか?
難しい専門用語を避け、こちらが理解できるように言葉を選んで説明してくれるかは、重要なポイントです。 - レスポンス(返信)は早いか?丁寧か?
問い合わせへの返信速度や、メールの文面などから、誠実さや仕事への取り組み姿勢がある程度うかがえます。 - 約束を守ってくれるか?(例:資料送付の期日など)
小さな約束でも、きちんと守ってくれるかどうかは、信頼関係の基本ですよね。
どんなに素晴らしい技術や実績があっても、担当者との相性が悪く、コミュニケーションが円滑に進まなければ、ストレスが溜まってしまいますし、最終的に出来上がるホームページの質にも影響が出かねません。



この人になら、安心して任せられそうだな



この人と一緒に、良いものを作っていけそうだな
そう直感的に思える相手かどうか、あなたの感覚も大切にしてみてくださいね。
具体的な選定ステップ:問い合わせから契約までの流れを解説
さて、「失敗しないための3つのポイント」を押さえたところで、いよいよ具体的な制作会社の選定ステップに進みましょう!
「よし、探すぞ!」と思っても、



何から手をつければ良いか分からない…
という方もいらっしゃるかもしれません。



大丈夫です、ご安心ください!
一般的なホームページ制作会社の選定は、大きく分けて以下のような流れで進んでいきます。
これらステップを一つずつ丁寧に踏んでいけば、あなたに合った制作会社が見つかるはずです。



ここからは、それぞれのステップで何をすべきか、具体的に見ていきましょう
ステップ1:依頼先候補のリストアップ方法
まずは、候補となる制作会社やフリーランスを探し、リストアップするところから始めます。
効率的に情報収集するための方法としては、以下の方法が考えられます。
- インターネット検索
「ホームページ制作 会社 〇〇(地域名)」や「ホームページ制作 〇〇(業種)」「Webデザイン 会社 おしゃれ」など、あなたの目的や地域、重視するポイントに合わせてキーワード検索してみましょう。制作会社自身のサイトや、比較サイト、ブログ記事などが見つかるはずです。 - 知人・取引先からの紹介
もし周りにホームページ制作を依頼した経験のある方がいれば、おすすめの会社を聞いてみるのも良い方法です。実際に利用した人の生の声は、非常に参考になりますよね。 - SNSでの検索
X(Twitter)などで、「#ホームページ制作」「#Webデザイン」といったハッシュタグで検索すると、フリーランスのデザイナーや小規模な制作会社が見つかることもあります。ポスト内容から、実績や人柄が垣間見えることも。
情報収集する中で、



おっ!良さそう…!
と感じた会社やフリーランスを、まずは5〜10社ほどリストアップしてみましょう。
その際、それぞれの会社のウェブサイトを見て、「制作実績」「得意分野」「料金体系(目安でも)」などを簡単にメモしておくと、後で比較しやすくなりますよ。
そして、そのリストの中から、特に



自分の目的やイメージに合っていそうだな
と感じる会社を、最終的に3社程度に絞り込むのがおすすめです。
あまり多すぎると比較検討が大変になりますし、少なすぎると有効な比較ができない可能性があるからです。



絞り込んだ3社に、次のステップである「問い合わせ」をしてみましょう。
ステップ2:効果的な問い合わせとRFP(提案依頼書)作成のコツ
候補を3社程度に絞り込んだら、いよいよ実際に連絡を取ってみます。
多くの制作会社のウェブサイトには、「お問い合わせフォーム」やメールアドレスが記載されていますよね。
ここで大切なのは、「とりあえず話を聞いてみたい」という漠然とした問い合わせではなく、できるだけ具体的に、あなたの状況や要望を伝えることです。
なぜなら、具体的な情報を伝えることで、制作会社側も



このお客さんには、こういう提案ができそうだな
と考えやすくなり、より的確な返答や、その後の打ち合わせでのスムーズな進行が期待できるからです。
問い合わせ時に伝えておきたい主な情報は、以下の通りです。
- あなたの会社名(または屋号・氏名)と担当者名、連絡先
- 現在のビジネスの概要(どんな事業をしているか)
- ホームページ制作を検討している理由・目的(何を達成したいか)
- ターゲットとなる顧客層
- 現在のウェブサイトの有無(リニューアルの場合)
- 希望するホームページのイメージ(参考サイトがあれば伝える)
- 必須で入れたい機能やコンテンツ(例:ブログ機能、予約フォーム、事例紹介など)
- おおよその予算感(もし決まっていれば)
- 希望する納期(もしあれば)
これらの情報を全て完璧に書く必要はありませんが、伝えられる範囲で具体的に記載することで、相手も真剣度を理解してくれます。
より本格的な依頼には「RFP(提案依頼書)」の作成も有効
もし、作りたいホームページの要件がある程度固まっている場合や、複数の会社から質の高い提案を比較検討したい場合は、「RFP(Request for Proposal:提案依頼書)」という書類を作成するのも非常に有効です。
RFPには、上記の問い合わせ情報に加えて、より詳細な要件(サイト構成案、機能要件、デザイン要件、運用体制など)をまとめて記載します。
ただ、RFPの作成には手間がかかるので、比較的小規模なサイトや、まだ要件が固まっていない段階では、まずは丁寧な問い合わせから始めるのが良いでしょう。



問い合わせの返信内容やスピード感も、その会社の姿勢を知る上で参考になりますよ
ステップ3:打ち合わせ・ヒアリングで必ず確認すべき質問リスト
問い合わせをして、制作会社から「ぜひ一度お打ち合わせを」という返答があったら、いよいよ直接話を聞くステップです。
この打ち合わせ(ヒアリング)は、制作会社があなたの要望を理解する場であると同時に、あなたがその会社を見極めるための非常に重要な機会となります。



何を話せばいいんだろう…
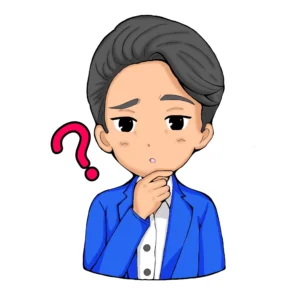
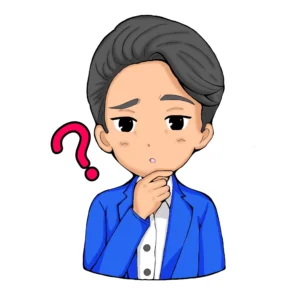
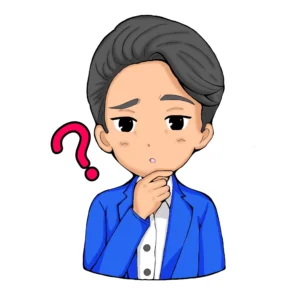
何を聞けばいいんだろう…
と不安になるかもしれませんが、心配いりません!
事前にいくつか質問を用意しておけば、落ち着いて臨むことができます。
ここでは、打ち合わせで必ず確認しておきたい質問をリストアップしてみました。



ぜひ参考にしてくださいね
【目的・提案について】
- 私たちのビジネスやホームページの目的について、どのように理解されましたか?
- 私たちの目的を達成するために、どのようなホームページが最適だと考えますか?
- 具体的な提案はありますか?
【実績・得意分野について】
- 私たちの業種や目的に近い制作実績があれば、具体的に教えていただけますか?
- 御社の最も得意とする分野(デザイン、システム、マーケティングなど)は何ですか?
- 今回のプロジェクトを担当されるチーム(または担当者)の経験やスキルについて教えてください。
【制作プロセス】
- 制作はどのような流れ(スケジュール)で進みますか?
- 各ステップで私たちがやるべきことは何ですか?
- 修正の依頼は何回まで可能ですか?また、どの段階で可能ですか?
- 制作途中の進捗は、どのように報告・確認させていただけますか?
【費用・契約について】
- 概算の費用感はどれくらいになりそうでしょうか?(詳細な見積もりは後日でもOK)
- 見積もりに含まれる作業範囲と、含まれないもの(オプション費用など)を教えてください。
- サーバーやドメインの契約・管理はお願いできますか?その費用は別途かかりますか?
- 契約前に、どこまでの作業(提案、デザイン案など)を無料でお願いできますか?
【コミュニケーション・サポートについて】
- 主な連絡手段(メール、電話、チャットツールなど)は何になりますか?
- ホームページ公開後の保守・運用サポートの内容と費用について教えてください。
- 簡単な更新作業(ブログ投稿など)は、自分たちで行えるように教えていただけますか?



これらの質問を全て投げかける必要はありませんが、あなたが特に重視するポイントは、確認するようにしましょう
そして、質問への回答だけでなく、担当者の話し方や説明の分かりやすさ、熱意といった「人となり」も、しっかりと感じ取ることが大切です。



この人となら、良いものが作れそうだ!
と思えるかどうかが、重要な判断基準になりますよ。
ステップ4:提案内容と見積もりを正しく比較検討するポイント
打ち合わせ(ヒアリング)を経て、各社から具体的な提案書と見積書が提出されたら、いよいよ比較検討のステップです。
多くの場合、3社程度の提案を見比べることになるかと思いますが



どこをどう比べればいいの?
と迷ってしまうかもしれませんね。
特に、見積もり金額だけを見て、



一番安いところにしよう!
と早合点してしまうのは、失敗のもとになりやすいので注意が必要です!
提案内容と見積もりを正しく比較検討するためには、以下のポイントを押さえることが大切です。
- 提案内容は、あなたの目的や課題を解決するものになっているか?
ヒアリングで伝えた目的や課題に対して、的確な解決策が提案されているかを確認しましょう。単に見た目が良い、機能が多いというだけでなく、「目的達成に繋がるか?」という視点で評価しましょう。 - 見積もり金額だけでなく、その「内訳」と「作業範囲」を比較する
見積もり金額は当然気になりますが、それ以上に「何にいくらかかっているのか(内訳)」と「どこまでの作業が含まれているのか(作業範囲)」をしっかり比較することが重要です。 - 費用対効果(コストパフォーマンス)で判断する
単純な安さだけでなく、「この提案内容と品質で、この価格は妥当か?」という費用対効果の視点で判断しましょう。多少高くても、目的達成への貢献度が高く、長期的なサポートも期待できるのであれば、結果的にコスパが高いと言えるかもしれません。 - 担当者の熱意や相性も考慮に入れる
提案内容や見積もりだけでなく、打ち合わせでの担当者の対応や熱意、コミュニケーションの取りやすさといった「人」の部分も、最終的な判断材料に加えましょう。信頼できる相手かどうかも、プロジェクト成功の鍵を握ります。 - 不明点は必ず質問する
提案書や見積書を見て、少しでも疑問に思う点や不明な点があれば、遠慮せずに質問しましょう。曖昧なまま進めてしまうと、後々トラブルの原因になりかねません。質問への回答の仕方からも、その会社の誠実さが見えてくるはずです。
これらのポイントを踏まえて、総合的に「どの会社が、自分たちの目的達成に最も貢献してくれそうか?」を判断することが、後悔しない会社選びのコツです。
ステップ5:契約前に最終確認!後悔しないためのチェックリスト
複数の提案を比較検討し



この会社にお願いしよう!
と心に決めたら、いよいよ契約です。
でも、契約書にサインする前に、もう一度だけ立ち止まって、最終確認をしっかり行いましょう!
契約内容は、後で「知らなかった」「聞いていなかった」とならないように、細部まで目を通し、疑問点は解消しておくことが重要です。



契約書って難しそうで、読むのが面倒だな…
と感じるかもしれませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、ここは頑張りどころです!
契約前に最低限チェックしておきたい項目をリストにまとめました。ぜひ活用してください。
- 契約期間と更新条件
契約はいつからいつまで有効か?自動更新なのか、都度更新なのか? - 作業範囲と納品物
見積もりに含まれる最終的な作業範囲は明確か?納品されるものは何か? - 制作スケジュールと納期
各工程のスケジュールと最終的な納期は明記されているか?遅延した場合の取り決めはあるか? - 支払い条件と時期
費用の総額、支払い方法(一括、分割など)、支払い時期(着手時、納品時など)は明確か? - 修正対応
修正可能な回数や範囲、追加修正の場合の費用は明確か?どの段階で修正依頼が可能か? - 著作権の帰属
制作されたホームページのデザインやコンテンツの著作権は、どちらに帰属するのか?(通常は依頼主側に譲渡されることが多いですが、要確認) - サーバー・ドメイン
サーバーやドメインの契約・管理は誰が行うのか?費用負担はどうなるのか? - 公開後の保守・運用サポート
サポートの範囲(更新作業、障害対応、バックアップ等)、期間、費用は明確か?サポートが不要な場合はその旨も確認。 - 機密保持
打ち合わせ等で提供した自社の機密情報が、適切に扱われるか?(機密保持契約(NDA)を別途結ぶ場合も) - 解約条件
万が一、契約を途中で解除する場合の条件や費用負担はどうなるのか? - 担当者と連絡体制
プロジェクト期間中の主な担当者と、緊急時の連絡先は明確か?
これらの項目を一つずつ確認し、もし不明な点や納得できない点があれば、遠慮なく制作会社に質問・相談しましょう。
契約内容に双方が合意できたら、いよいよ正式に契約締結となります。



これで、あなたのホームページ制作プロジェクトが本格的にスタートしますね!
気になる費用相場と料金体系の注意点【予算で後悔しないために】
ホームページ制作を依頼する上で、やはり一番気になるのは「費用」のことではないでしょうか。



一体いくらくらいかかるんだろう?
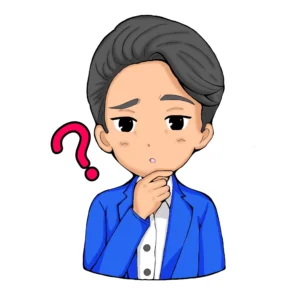
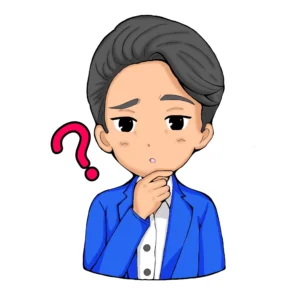
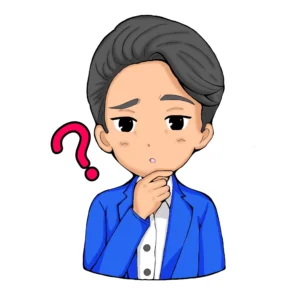
見積もりって、どう見ればいいの?
といった疑問や不安を感じている方も多いと思います。
僕もフリーランスとして活動する中で、お客様から費用に関するご相談をいただくことは非常に多いです。
ホームページ制作の費用は、サイトの種類や規模、依頼先(制作会社かフリーランスか)、機能の複雑さなどによって本当にピンキリです。
だからこそ、ある程度の相場感を知っておき、見積もりを見る際の注意点を押さえておくことが、予算で後悔しないために大切になります。



ここでは、気になる費用相場と料金体系について、注意点も交えながら解説していきますね
ホームページの種類別!制作費用の目安はいくら?
ホームページ制作って、大体いくらくらいかかるの?
という疑問にお答えするために、一般的なホームページの種類別に、大まかな費用相場の目安を示してみましょう。
ただし、これはあくまでも一般的な目安であり、依頼する会社やフリーランス、求めるデザインの質、機能の複雑さによって大きく変動します。
特に、フリーランスに依頼する場合は、これよりも安価になる傾向があります。(僕も格安で提供しています!)
参考程度にご覧くださいね。
| ホームページの種類 | 費用相場の目安 (制作会社依頼) | 主な目的・用途 |
|---|---|---|
| シングルページサイト | 10万円~30万円 | 特定の商品・サービスの紹介、キャンペーン告知など |
| コーポレートサイト (小規模) | 30万円~80万円 | 会社案内、事業紹介、採用情報 (5~10ページ) |
| コーポレートサイト (中規模) | 60万円~200万円 | 詳細な事業紹介、実績紹介、ブログ機能等 (10~30ページ) |
| 店舗・サービス紹介サイト | 40万円~ | 店舗情報、メニュー紹介、予約機能 (簡易なもの) |
| 採用サイト | 50万円~150万円 | 企業の魅力発信、求人情報、応募フォーム |
| ECサイト (小規模) | 50万円~200万円 | 商品数が比較的少ない、基本的なカート・決済機能 |
| ECサイト (中~大規模) | 100万円~数百万円 | 多数の商品、複雑な機能、基幹システム連携など |
| オウンドメディア | 20万円~500万円 | ブログ記事等による情報発信、コンテンツマーケティング |
(※上記は初期制作費用のみの目安です。サーバー代、ドメイン代、公開後の保守・運用費用は別途かかる場合が多いです。)
見ていただくと分かる通り、かなり幅がありますよね。



そこで、次の「見積もりでチェックすべき項目」が重要になってくるわけです
見積もりでチェックすべき項目:どこまでが料金に含まれる?
制作会社から見積書が出てきたとき、合計金額だけを見て「高い!」「安い!」と判断するのは危険です。
大切なのは、その金額に「何が含まれていて、何が含まれていないのか」を把握すること。
見積もり内容をしっかり確認しないと、



これも別途費用がかかるの!?
といった、後々のトラブルに繋がりかねません。
見積書を受け取ったら、以下の項目が明確に記載されているか、必ずチェックしましょう。



もし記載がなかったり、曖昧だったりする場合は、遠慮なく質問してくださいね
- 企画・構成費
サイト全体の設計、コンテンツ企画、ワイヤーフレーム(設計図)作成などの費用が含まれているか? - デザイン費
トップページ、下層ページそれぞれのデザイン作成費用。デザイン案はいくつ提案されるのか? - コーディング費(HTML/CSS/JavaScript)
デザインをWebページとして表示させるための作業費用。レスポンシブ対応(スマホ表示)は含まれているか? - CMS構築費(WordPressなど)
自分で更新できるシステム(CMS)を導入する場合の費用。どのCMSを使うのか?初期設定やカスタマイズ費用は? - コンテンツ制作費
掲載する文章(ライティング)や写真・イラスト素材の作成・購入費用は含まれているか?
(含まれない場合が多いので注意) - 機能開発費
お問い合わせフォーム、予約システム、検索機能など、特別な機能を実装する場合の費用。 - ページ数
見積もり金額に含まれるページ数は何ページか?ページ追加の場合の単価は? - サーバー・ドメイン関連費
サーバー契約代行、ドメイン取得代行、サーバー設定費用は含まれているか?年間の維持費は別途かかるのか? - SEO対策費
基本的な内部SEO対策(タイトル設定、見出し構造など)は含まれているか?
より高度なSEO施策はオプションか? - 公開作業費
完成したサイトをインターネット上に公開する作業費用。 - 修正対応
制作途中や納品後の修正は、何回まで、どの範囲まで無料か?それを超える場合の費用は? - 打ち合わせ費
打ち合わせの回数や時間に制限はあるか?遠方の場合は交通費がかかるか? - 保守・運用サポート費
公開後のサポート(バックアップ、セキュリティ対策、更新代行など)は含まれているか?
月額または年額でいくらかかるのか?
これらの項目を一つ一つ確認し、作業範囲と費用を明確にすることが、予算オーバーや認識のズレを防ぐための鍵となります。



面倒に感じるかもしれませんが、ここをしっかり押さえておけば、安心してプロジェクトを進めることができますよ
「安い!」だけで決めないで!追加費用が発生しやすいケースとは?



できるだけ費用を抑えたい!
というのは、誰しもが思うことですよね。
僕も節約家なので、その気持ちは痛いほど分かります!
しかし、ホームページ制作において、単純な見積もり金額の安さだけで飛びついてしまうのは、実は結構危険なんです。
なぜなら、



一見安く見えたけど、後からどんどん追加費用が発生して、結局高くついてしまった…
というケースが、残念ながら少なくないからです。
どんな場合に追加費用が発生しやすいのか、代表的なパターンを知っておきましょう。
- 修正回数が契約範囲を超えた場合
「修正は2回まで無料」といった契約で、3回目以降の修正を依頼すると追加費用が発生します。デザインや内容にこだわりたい場合は、修正回数に余裕があるか、追加修正の費用を確認しておきましょう。 - 制作途中で仕様変更や機能追加を依頼した場合
最初の計画になかったページや機能の追加を依頼すると、当然ながら追加費用がかかります。「やっぱりこういう機能も欲しいな…」となりがちな方は、初期段階で要件をしっかり詰めておくか、柔軟に対応してくれる会社を選ぶ必要があります。 - 提供する素材(文章、写真など)の準備が遅れた場合
ホームページに掲載する文章や写真などを自分で用意する契約の場合、その準備が遅れると、制作スケジュールが遅延し、追加の工数費用を請求される可能性があります。 - 写真やイラストなどの素材費用
高品質なストックフォトや、オリジナルのイラスト制作を依頼する場合、別途費用がかかることが一般的です。見積もりに素材費が含まれているか確認しましょう。 - サーバー・ドメインの費用
見積もりには制作費しか含まれておらず、サーバー代やドメイン代が別途必要になるケースは多いです。年間で数千円~数万円程度の維持費がかかります。 - 公開後の更新・修正作業
保守契約を結んでいない場合、公開後にちょっとした修正や更新を依頼するたびに、作業費用が発生します。「自分で更新できる範囲」と「依頼が必要な範囲」を把握しておくことが大切です。 - 想定外の作業が発生した場合
例えば、既存サイトからのデータ移行が複雑だったり、特殊なブラウザ対応が必要になったりした場合など、予期せぬ作業が発生し、追加費用となることも稀にあります。
追加費用が発生すること自体が悪いわけではありません。
見積もり段階で、



追加費用が発生する可能性があるとしたら、どのようなケースですか?
と正直に聞いてみるのも良いでしょう。
誠実な会社であれば、きちんと説明してくれるはずです。
安さだけに惑わされず、トータルでかかる費用とリスクを考慮して、納得のいく会社選びをしてくださいね。
【FAQ】ホームページ制作会社選びでよくある疑問にお答えします!
ホームページ制作会社の選び方について、色々な情報をお伝えしてきましたが、それでもまだ「ここがよく分からない…」「こういう場合はどうなの?」といった疑問が残っているかもしれませんね。



ここでは、そんなホームページ制作会社選びに関する「よくある疑問」について、Q&A形式で、できるだけ簡潔にお答えしていきますね!
- フリーランスと制作会社、結局どっちに依頼すべき?
-
どちらが良いかは、あなたの状況や重視するポイントによります。
フリーランスは、一般的に費用を抑えやすく、直接制作者とやり取りできるので柔軟な対応やスピード感が期待できるのがメリットです。スキルや信頼性に個人差が大きい点や、一人で対応できる範囲が限られる点は注意が必要です。
制作会社は、複数人体制で品質が安定しやすく、幅広い対応力や継続的なサポート体制が期待できるのが強みでしょう。その分、費用は高くなる傾向があります。
「費用を抑えたい」「特定のスキルを持つ人に頼みたい」ならフリーランスも良い選択肢ですが、「信頼性や幅広い対応力、継続サポート」を重視するなら制作会社が安心です。
プロジェクトの規模や予算、求める品質などを考慮して、ご自身に合った方を選んでみてください。
- 見積もりは何社くらい取るのがベスト?比較の仕方は?
-
3社程度から見積もりを取るのがおすすめです。
多すぎると比較検討が大変になりますし、少なすぎると相場観が掴みにくく、最適な提案を見逃す可能性もあるからです。
比較する際は、見積もり金額だけを見るのではなく、必ず「内訳」と「作業範囲」を確認しましょう。
何にいくらかかっていて、どこまでの作業が含まれているのかをしっかり比較することが大切です。
さらに、「提案内容があなたの目的達成に合っているか」「担当者の対応は信頼できそうか」といった点も合わせて総合的に判断するのが、良い比較の仕方だと思います。
- 制作実績(ポートフォリオ)で特に重視すべき点は?
-
まず、あなたの業種や作りたいホームページの目的に近い実績があるかどうかです。
次に、見た目だけでなく、実際にサイトを操作してみて、情報が分かりやすく整理されているか、使いやすいか(UI/UX)という点も確認しましょう。
単なるデザイン集として見るのではなく、「自分の目的達成に役立つか?」という視点でチェックすることが重要です。
- デザインがカッコよければ良いホームページと言える?
-
「デザインがカッコいい=良いホームページ」とは、必ずしも言えません。
なぜなら、ホームページの本来の目的は、見た目の良さだけではなく、ビジネス上の成果(集客、売上、問い合わせ獲得など)に繋げることだからです。
どんなにカッコよくても、情報が見つけにくかったり、使いにくかったり、ターゲットに響かなかったり、検索エンジンで見つけてもらえなかったりでは、目的を達成できませんよね…。
大切なのは、デザイン性と、目的達成に必要な機能性、使いやすさ、情報の内容、SEO対策などのバランスです。
- ホームページ公開後の保守・運用サポートは依頼すべき?
-
あなたの状況やホームページの種類によります。
ホームページは作って終わりではなく、公開後もソフトウェアの更新、セキュリティ対策、バックアップ、記事の更新、情報の修正など、定期的なメンテナンスが必要になることが多いです。
もし、ご自身でこれらの対応をするのが難しい場合や、本業に集中したい場合は、保守・運用サポートを依頼するメリットは大きいでしょう。
専門家に任せることで、安心してサイトを運営できますし、トラブル発生時も迅速に対応してもらえます。
ただし、当然ながらサポートには費用がかかります(月額または年額)。
どこまでの作業を自分でできて、どこからをプロに任せたいのかを考え、サポート内容と費用を比較検討して判断するのが良いでしょう。
まとめ:HP制作会社選びは目的・実績・相性が鍵!
今回は「ホームページ制作会社の選び方で迷っている方」に向けて、
- ホームページを作る目的の明確化
- 制作会社の種類とそれぞれの特徴
- 失敗しないための3つの選び方ポイント
- 具体的な選定ステップと費用面の注意点
上記について、ホームページ制作者としての経験を交えながら、お話してきました。



ホームページ制作会社の選び方、本当に迷いますよね
僕も制作者としての経験や調査から痛感していますが、価格だけでなく
- 目的との合致度
- 制作実績
- 担当者との相性
上記の3つが特に大切なんです!
3つのポイントをしっかり見極めることができれば、あなたのビジネスを心から応援してくれる、信頼できるパートナーにきっと出会えますよ!
焦らず、これらの視点を持ってじっくり比較検討してみてくださいね。



あなたのビジネスが飛躍する、最高のホームページが完成することを心から応援しています!